こんにちは。知的障害のある発語ゆっくりな娘を育てるIT系ワーママのりょうこです。
小さく産まれた娘のはーちゃん(2021年現在5歳)ですが、一番遅れていて心配なのは発語です。
小児の発語について学ぶために聞いている小児発語のプロ【言語聴覚士なな先生】のVoicyチャンネルの2021年11月後半分をまとめました。
お話すべての書きおこしではなく、キーワードを書き留めていますので、詳しい内容、正しい内容は必ず本編を聞いて下さいね。 やさしい声と語り口で聞いているだけで癒やされます。
それでは、いってみよ~~
なな先生のことばの発達ラジオ 2021年11月分後半

2021/11/17 助詞は必要があるから覚える

今回は、助詞の獲得のお話です。
大人になると無意識に使っている助詞。「の」にも所有と位置関係の「の」があって、それぞれ獲得できる時期が違うなど、興味深いお話でした!
なな先生はご自身が企画運営するの販売サイト、コトリドリルで「助詞メダル」という商品を販売しています。助詞に特化した商品はなかなか見かけないので、気になる方はぜひチェックしてみてください!
助詞とはなんでしょう。
「私はテレビを見る」の、「は」と「を」が助詞。
助詞の例:が・で・に・を・の・と・も・から・こそ・しか・まで
非常に短いが、言葉に役割を与える大切な言葉。助詞がないと片言のお喋りのように聞こえる。(はーちゃん テレビ みるー)
ことばの発達では、先に覚えるのは「1つだけ取り出しても意味がある言葉」。
助詞の獲得はその後になる。
会話で助詞を正確に使いこなせるのは小学校1~2年生くらい(書き言葉では大人でも間違えることがある)。獲得に7年くらいかかる。
助詞にも難易度があり、「と」や(所有の)「の」は2歳くらいから使える。
例:

なんのアイスがたべたい?

いちごとバニラー

このおもちゃはだれの?

はーちゃんのー
上の例のような所有の「の」は早く覚えるが、位置関係の「の」は難しい。
例:わにさんのうえにかばさんがいる。
助詞には少し違うだけで意味が全然かわってしまうという難しさがある。
- りんごのうえ
- りんごがうえ
りんごの位置が違うことに注意!
助詞が大切になるのは、二人以上の人が関係するとき。
例えば、大きなかぶのお話で出てくるフレーズを考えてみよう。
「おじいさんがかぶをひっぱって。おばあさんがおじいさんをひっぱって」
助詞があれば、どっちがどっちをひっぱっているかすぐわかる。では助詞がないと?
「おじいさん かぶ ひっぱって」
「おばあさん おじいさん ひっぱって」
わかりますか?
かぶは物なのでおじいさんをひっぱらない。
おじいさんとおばあさんはどちらも人なのでどちらもひっぱることができる。
だから
「おじいさん かぶ ひっぱって」←助詞がなくても、どちらがひっぱってるかわかる
「おばあさん おじいさん ひっぱって」←助詞がないと、だれがひっぱってるかわからない
大きなかぶのお話にはさらに秘密が。
幼児向けの本と小学生向けの本では言い回しが異なる。
「おばあさんがおじいさんをひっぱって」
「かぶをおじいさんがひっぱって」
「おじいさんをおばあさんがひっぱって」
「を」と「が」の位置が入れ替わっている。
幼児は「が」と「を」を完全に使いこなしているわけではなく、「おばあさんがおじいさんをひっぱって」の順番のほうがより理解しやすい。
日本語では、助詞の獲得・理解が進むと、言葉の順番が入れ替わっても文の内容を理解できるようになる。それが助詞の役割。

はーちゃんは、助詞はまだ使えないと思っていたけど、「はーちゃんの!」は言うよね

確かに言うかも!
「大きなかぶ」は好きだよね。今度読んであげようかな。
2021/11/20 3歳4歳、遊びのなかでことば育て

今回は、おうちでできることばの発達の促し方のお話です。
これぞ、発達ゆっくりっ子の親であるわたしたちが待っていた内容ですね~
今回の内容は
- ごっこ遊びや見立て遊びを取り入れる
- 繰り返しを取り入れる
の2つです。
言語聴覚士さんが良く聞かれる質問にこんなものがある。
想定は3~4才のお子さん:

うちの子はことばが遅いのですが、なにかことばのために特別な練習やトレーニングをしたほうが良いでしょうか?
この質問に対する専門家のよくある回答はこんな感じ。
まずは遊びの中で、生活の中でことばを育むはぐくむのが一番ですよ。
特別な練習は5才~6才になったときにどうしても必要になったら考えましょう。
今は楽しく過ごして下さいね。
この回答は「なにもしないでいいですよ。そのままでほうっておいていいですよ。」という回答ではない。
しかし、下記のような誤解をされることが多い。
- STさんは何にもしなくていいって言ってる!
- 今ことばを伸ばしたいのに、様子見でいいって言われた!
- 親が焦りすぎと言われてしまった!
どれもSTさんの真意ではなく、遊びや生活の中で育めることばはたくさんあると言いたいのだが限られた相談時間のなかで伝わらないことが多い。
おうちの中・生活の中・遊びの中でできることば育て~大人が工夫できること~
想定年齢:言語能力が3~4才くらいの子ども。実年齢よりもことばの発達がゆっくりの子にもあてはまる。
- 1:ごっこ遊びや見立て遊び(生活や大人の様子を再現する遊び)を取り入れる
- ごっこあそび:
例:おままごと・おみせやさんごっこ・おいしゃさんごっこ
ごっこあそびは生活をロールプレイングすることにより、台詞を通してことば、やりとり、フレーズを学ぶことができる。
「この状況のとき、この立場のこの人はこういうことをする」という型を学ぶ。
発達学ではこの型のことをスクリプトという。
典型的な場面・状況を遊びの中で再現すると、語彙表現の獲得やいろいろなことへの興味関心が広がっていく。
見立て遊び:
例:積み木をスプーンに見立てて、ぬいぐるみにあーんするなど
その子の頭の中にはスプーンのイメージがしっかりあり、スプーンのつもりで遊ぶことができている。
頭の中でイメージを膨らませ、そのイメージのなかに乗っかっていくように作っていくのがことば。頭のなかでイメージを作ることが、ことばの学びの一歩。
- 2: 繰り返しを取り入れる
- 子どもは繰り返しが好き。
例えば絵本。
代表的な例:「大きなかぶ」
かぶが抜けるまで繰り返しが何度も続く。続くうちに繰り返しを楽しみに待つようになる。大人の世界でも「予定調和」という言葉がある。先が読めることが楽しみということがある。
例えばアニメ。
代表的な例:「アンパンマン」
ある程度物語の型や流れが決まっている。
バイキンマンがいたずらをして、アンパンマンがピンチになるが、顔を焼いてもらって、最後はアンパンマンが勝利してバイバイきーん
例えば幼児語。
子どもが好きなオノマトペ、擬音語、擬態語には繰り返しが使われている。
(とんとん、ぶーぶー、ないない、わんわんなど)
子どもは繰り返しの言葉を好む。耳心地がよく、言いやすい。
繰り返しにより、ことばの練習を積んでいることになる。
例えば、お人形が6体あったとき全員におやすみなさーいとお布団をかける。6回「おやすみなさーい」と言うことにより、ことばを6回練習していることになる。
お店屋さんごっこの「いらっしゃいませー、○○くださーい」を5回繰り返すと、5回練習したことになる。
公文のくるくるチャイム。ボールが5個あることで5回練習できるようになる。
繰り返しの回数について:
遊びの中の繰り返しは欲張りすぎないことがポイント。
くるくるチャイムの5個は、集中力が切れず、もうちょっとやりたいかな~で終わらせられるちょうどいい回数。
全部無くなって、「なくなった」という経験をすることも大切。
ちょっと物足りないかなーという気持ちが、次の遊びへのモチベーションになる。
目安は5個、5回。
もっと小さくて集中力が続かない子どもは、3個、3回から始めるのが良い。

ことばの練習は、工夫次第で家の中でたくさんできるのね。
ちょっと反省です…

おままごとかー、つきあうのやだなー

にぃにぃ、いらっしゃいませ、しようよー
2021/11/23 3歳4歳遊びのなかでことば育て 応用編

今回は、前回のおうちでできることばの発達の促し方の続きです!
楽しみですね~
今回の内容は
- 口の形・動きを見せてマネをしてもらう
- 色を遊びに取り入れる
- 数を遊びに取り入れる
- ものの位置・場所を表す表現を遊びや普段の生活に取り入れる
の4つです。
前回のおうちの中・生活の中・遊びの中でできることば育て~大人が工夫できること~の続き
前回は子どもからの発語を促す方向の工夫だったが、今回は大人がちょっとだけ積極的になってみる応用編4つ。
基本編ができていることが前提。お勉強や強要になることなく、あくまでも「遊びのなかで」「楽しいなかで」を忘れずに。
- 1. 口の形・動きを見せてマネをしてもらう
- お口の動きに注目してもらう。
例:
おままごとで食べる真似をして”あーんもぐもぐ”としているときに、口の動きをしっかりみてもらう。
口の形、声がどのように出ているかを見てもらうことでマネをしやすくなる。
特に最近はマスクをしていることが多いので、おうちではマスクをとろう。
唇をぶるぶると振わせたり、ほっぺたを膨らませたりぷっと音をさせたり、アイスをぺろぺろしたり、あっかんべーをしたり
いろいろな口の動きを見せて、あわよくばマネをしてもらおう。
ま行、ぱ行、ば行のような唇で出す音は比較的簡単。
例:ぶっぶー、パン、もも - 2. 色を遊びに取り入れる
- 色は音がとらえやすくマネしやすい2文字のものが多く、練習しやすい
例:
あお(全部母音)
あかは、”k”の音が難しいので、”あた”や”ああ”になるかもしれないがそれでOK
色の遊びの例:
同じ色同士を集めるあそび
色ごとに仲間分けをするあそび
色を使うと、「あかいぼうし」、「あかいさかな」のように2語文の練習につかえる
- 3. 数を遊びに取り入れる
- 数を取り入れた遊びの、一番最初は「ものをならべる」ところからはじめる。
ならべるの次のステップは、並べたお人形それぞれに食べ物をあげていく(一対一対応を学ぶ)
数を取り入れた遊び例:
ひとつずつ指さしていく
もう一度やりたいときに「もういっかーい」と言う
カウントダウン(3,2,1スタート!)はわくわく感があり子どもは好む - 4. ものの位置・場所を表す表現を遊びや普段の生活に取り入れる
- ものの位置、場所を表す表現を取り入れる
例:
「隣においてね」「後ろにあるよ」「下に落ちちゃったね」「中に入れてね」「上に置いてね」など
上記が難しかったら、
「ここ・そこ」「これ・それ」「こっち・あっち」
のような、近くと遠くの表現で始める。
「ここ・そこ」を多用するようになったら、「この上に」「この下に」など、ここそこだけにしない表現にかえる
「どこ」について
例えば子どもに「お兄ちゃん、どこ?」と質問して「お兄ちゃんトイレー」と教えてくれたら、「どこ」の意味がわかっているということ
子どもに「どこ?」と聞かれたときは、表現を増やしてあげるチャンス。
意識的に「○○の上だよ」のような表現を使ってあげる。
大人が感度を高めて投げかけをキャッチし、その子の段階にちょうど良い言葉かけをしてあげよう

たっくんが習っていた英会話も、数とか色とか位置(on, in, under)なんかを最初に繰り返し繰り返しやっていたのを思い出したわ

ことばの習得順序は、日本語でも外国語でもおんなじなのかなー
2021/11/26 -Tea Break- SNSで「ひどい支援者」の話をしない

今回は、Voicyのフォロアーさん1,000人突破記念の放送です!
おめでとうございます!!
「SNS発信でなな先生がやらないと決めたこと」についてだそうです。
今回は、先生個人の思いやポリシーについてのお話なので、内容のまとめはトピックをあげるにとどめておきます。先生のフェアで真面目なところと業界を思う強い気持ちが伝わってきます。素敵です。
内容が気になる方はぜひ放送をお聞き下さい!
SNS発信でなな先生がやらないと決めたこと
1.他の先生に対する批判をしない、
2.他の人から先生批判のメッセージが来たときにそれを公開しない
3.あたりまえの基準を上げすぎない
※あくまで先生のマイルールであり、当事者のみなさんが合理的配慮を求める声をあげることを認めないものではありません。とのことです。
2021/11/29 スピーチセラピスト直伝、伝わる話し方のコツ

今回は、Voicy社の企画「伝わる話し方のコツ」です。
言語聴覚士さん直伝。必聴ですね!
今回のテーマはVoicyの企画。
言語聴覚士として伝わるために話し方で気をつけていること(3選)
1.注目を引きつけてから話しはじめる。
いきなり話しかけることはせず、こちらに注目が向いていることを確認した上で話し始める。
注意散漫になっている場合
- 「○○さん」と話しかけてから本題に入る。
- 「ところで~」「まず~」のような聞いていなくてもよいパーツ、枠組みを作るフレーズを入れて、その間に聞く姿勢を作ってもらう。
子どもの場合は、注意の分配能力が乏しいので「○○しながら」にならないようにする。
2.しゃべるときの声の高さ、高いところを中心に低い音もまぜて高低差で抑揚をつける。
小さい子どもや赤ちゃんに話しかけるときに無意識に高めのトーンになることをマザリーズやCDS(Child Detected Speech)と言う。子どもに向けた万国共通の話し方。
このように、少し高めの音域で話したほうが注目をひきやすい。しかし、ずっと高音だと話す方も聞く方もお互い疲れてしまう。
高い音を中心に低い音も混ぜながら話すのが良い。
大事なことを言うときは、少し小さい声で低いところから始める。
高いところ、低いところをなめらかにつなげて抑揚をつけ、山を作る。
しゃべりの輪郭の高低差をしっかりあると、人の注意をひきつける話ができる。
3.滑舌は最低限、音を出す場所だけ気をつける
日本語の音は、口の中のどこ出す音なのか(舌の先端、喉の奥、のような場所)が決まっているので、それを間違えないように気をつけている。

人に伝わる話し方を覚えていると、学校や会社でも役に立ちそうね!

学校の先生も、ぼくたちが注目しているのを確認してからお話始めてるかも~
まとめ: 2021年11月後半の放送5本をご紹介しました
2021年11月後半の放送は5本でした。
助詞の獲得、3才・4才の遊びのなかでのことば育て(前後編)、Tea Breakを挟んで、伝わる話し方のコツについての情報がありました。
特に3才・4才の遊びのなかでのことば育て(前後編)では6つのポイントを具体的に教えてもらうことができました。すぐに毎日の遊びに取り入れられそうです!
どれも10~20分聞ける内容です。
Voicyはチャプター割がしてあったり、聞き取れるくらいの早回し(1.2倍~)で再生する機能もありますので、ぜひ先生の優しい生声を聞いてみてくださいね!

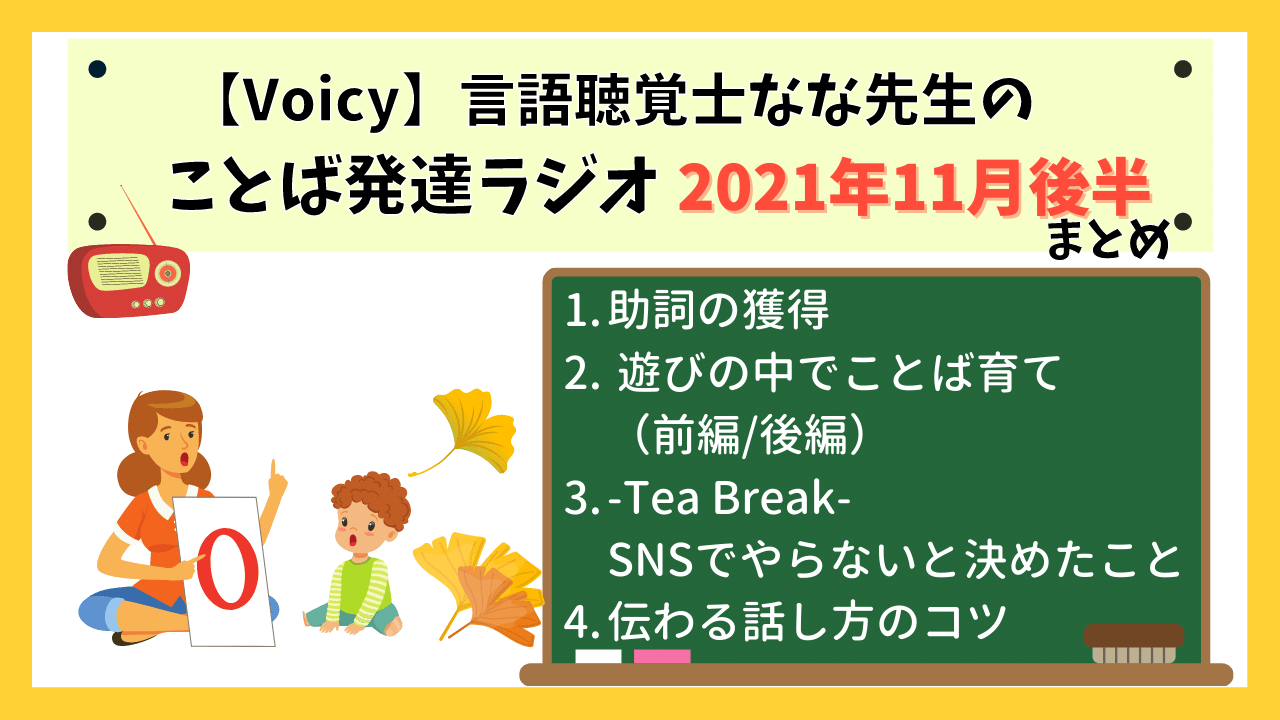


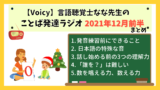


コメント